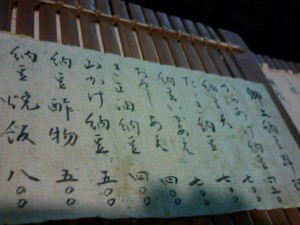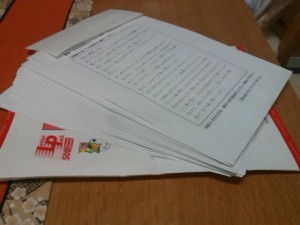フォーラムシアターという演劇の手法をつかって、NPO「子どもとメディア」の活動として学校現場と関わって5年になる。今日は、その脚本家とコーディネイター役のメンバーからSOSがあって、打ち合わせ。
このプロジェクトは、脚本家や役者、表現教育家がメンバーを組んで、学校に行き、表現ワークやお話作りのワークを積み上げて最後に提供するのが「フォーラムシアター」である。
まず役者たちによって、お父さんはテレビばかり、姉はケータイ、弟はゲームというメディア漬けの家族の1シーンが演じられ、コーディネイターが子どもたちから意見をもらって役者にオーダーし、即興で劇を演じ変えてゆきながら家族のコミュニケーションが感じられる芝居に変えてゆく。出される子どもたちの意見によって、やる度に結末は変わるから役者も即興力がある人でないとできない。
シアタープロジェクトと銘打って5年前から実施しており、学校が文科省からの助成金などを申請して呼んでくれる。5年間に九州だけでなく、島根や鳥取、山口など30以上の学校で上演してきた。
しかし・・である。子どもたちから出てくる意見から感じる子どもたちの現状が、もはや看過できないというのだ。
表に出てくる問題は「テレビを切るという選択肢が子どもから出てこなくなった」「目を合わせて会話するという意見が出なくなった」ということ。つまり、テレビが付きっぱなしで、目を合わせずに、ぼそぼそと聞かれたことに応えながら食事をしている子ども。子どもたちはそれでいいというのだ。それが日常だから違和感がないのだろう。
だが、もっと背景に「家族が関わろうとしない方向に向かう」「先の意見で上手くいかなかったら、それに積み上げるのではなく、全く別の提案をする」「意見は言うが、より詳しく聞かれると考えようとしない」など、今の子どもたちの大きな課題が見えている。
メディア漬けのためにコミュニケーションが上手くいかない家族をどうしたらいいか・・という課題をもってのフォーラムシアターだが、「それぞれの部屋で好きなことしたらいい」という意見には愕然としたという。
子どもたちの「失敗しても平気だよ」ということばが「だって本気じゃないもん」という意味だと、どれだけの教師が知っているだろう。勝負の結果で大事なのは「勝って嬉しい」ではなく「負けなくてよかった」であり、負けないためには勝負をしないことも子どもの選択肢であると、大人は知っているだろうか?
学校の日常の一部にしか関わらないフォーラムシアターのメンバーだが、演劇で鍛えた彼らの感性のアンテナは子どもたちの現状を鋭く感じ取って報告してくれた。
脚本の書き直し方向を話し合って終わったが、今の学校教育、子どもの育ちがこれでいいはずがない・・と、大きな課題を預けられた気がする。
保育に携わる全ての人へ、学びの場を提供します。
現場で必要とされる専門知識を、3か月で習得することができます
特定非営利活動法人 子どもと保育研究所 ぷろほ